寝る前にベッドの中で本を読む。
読んでいるうちに、だんだん眠くなってくるので、
そのままひっくり返して、枕元に置いたまま寝る。
どんな気に入った本でも、
やはり途中でちょっと飽きるので、
いつも本は数冊を同時進行である。
今も4冊、枕元に転がっている。(2023年1月なう)
すっと入っていけたお気に入りの本が4冊が、
枕元でチョウチョになっている。
どれも面白くて、ちょっと自慢したくなった。
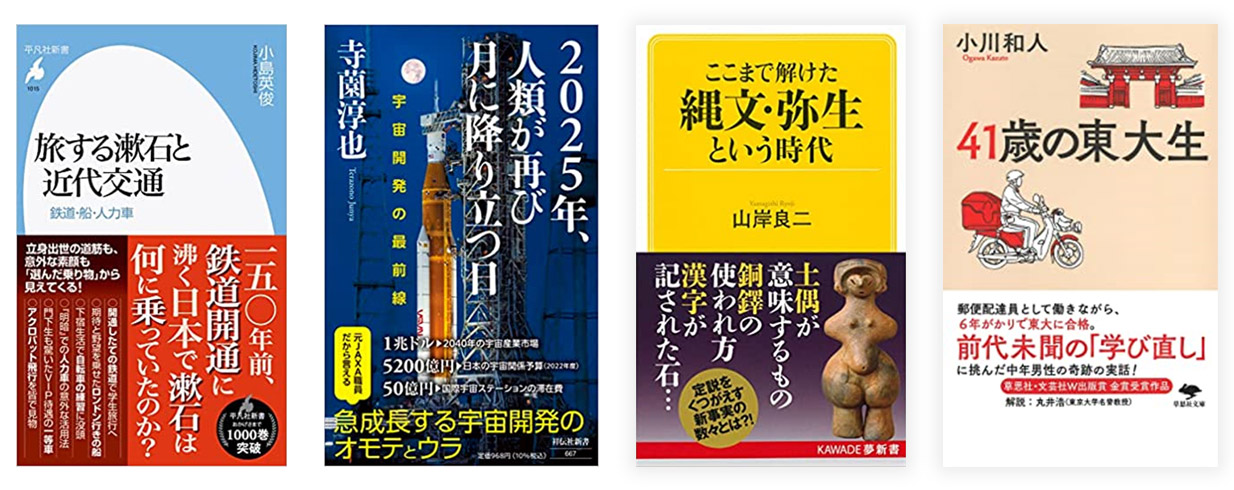
1)旅する漱石と近代交通(平凡社新書)
明治の年号とほぼ同じ年齢の漱石。
彼の随筆と鉄道網の発展をシンクロさせて、
当時の世相をよく現している本を見つけた。
もうその着眼点からして斬新、脱帽、期待度大である。
漱石が大人になった明治20年から40年ぐらいまでの話である。
時代は、
若い時ちょんまげを結っていましたという世代がまだ半分いるとき。
乗り物は殿さまのカゴと手漕ぎの舟しか見たことがなかったときから、
いきなり東京~京都を19時間でつなぐ鉄の塊が現れる。
果たして庶民はこれをどう受け入れたのであろうかに、興味がわく。
鉄道が明治何年にどことどこが開通したということは知識としてあっても、
その時にごくごく市井の人々が、どんな感じだったのかという想像はしにくい。
高嶺の花で市井の人々のものではなかったのかとか、
乗り心地は実用的であったのかなかったのかとか、
時刻表とか運休状況とか駅員の態度とか、
現場の雰囲気というものが知りたいところなのである。
小学生になって初めて自転車を買ってもらって、
もしくは高校生の時の原付バイクでひとり隣町に出た時、
あれを超す感動は、人生において、そうそうあるものではない。
苦みつぶした顔した明治のじいさんたちが(イメージ)、
こんな興奮をもって車窓を眺めていたのだろうかと思うと、
なにか微笑ましいのである。
2)2025年、人類が再び月に降り立つ日(祥伝社新書)
宇宙開発のニュースは、ロケットの発射の映像くらいしか見かけない。
たまにの単発の羅列では何が何だかわからない。
それらを順序だてて、過程というものを教えてもらって、
やっと情も興味も沸いてくるというものである。
宇宙開発は、
日本は、純粋に研究者や科学者の探求心の延長として開発されているが、
他の国々は、政治の手段や軍事開発として開発がなされている。
よって大統領が変わると
今までの計画がガラッと変わったりするので、
もったいない部分がかなり発生しているようである。
そして日本も、そうとばかり言っていられなくなり、
いくらかのきな臭ささが漂い始まっている政情だというようなことも書いてあった。
そういえばタモリさんがぼそりと、
「今の日本は、戦前の始まりですかね」と言ってましたね。
そんな中で現代の宇宙開発は、一段とカオス化してきて、
基礎研究を持っているNASAやJAXAが、
民間に手を貸すことによって、新たな動が始まっている。
この民間は開発中の研究者たちの給料を、
どうやって払っているのかが気になる所だが、
ノー天気な感想を言えば、間口が広がって多くの人たちが、
夢の世界にたずさわれるようになっていることはうらやましいところでもある。
私もあと30年若くて物理の点数があと45点ほど高ければ、
覗きに行ったかもしれない。(100点満点で)
3)ここまで解けた縄文弥生という時代(kadokawa夢新書)
古代の人たちとは、現代の人間と比較して、
人間としての能力が特別劣っていたわけではない。
文字と電気がなかっただけの話である。
もし古代の人たちに
今の小学生程度の基礎知識があったとしたならば、
今の文明は間違いなく違っていた。
今では当たり前の石油と医療も、
ここ100年の話でしかない。
青森の三内丸山遺跡も1700年続いている。
ここの食器に残っていた「木の実」を分析してみたら、
DNAの形状がそろっており、
農作物として栽培したものと判明する。
これだけの集団が、
建物の建造や農耕作業を協力し合っておこなうとは、
もうりっぱな「社会が構成されていた」といえるのである。
世界四大文明とは日本の教科書でしか見られないワードなのだが、
文明の定義を、
「集団の規模と期間・文化の継続・他集団との交易」
あたりだとすると、
縄文文化の方がずっと古い文明ということになる。
バブル期の宅地開発ラッシュで埋蔵文化財センターがてんてこ舞いだったのに、
宅地開発の縮小にともなって8割がセンターの閉所の憂き目にあっているなんて、
夢想の楽しさと現実の切実さと行ったり来たりの世界でした。
4)41歳の東大生(草思社文庫)
たとえば、草野球をやっている人たちは、
時には真剣に時には笑顔を交え、
終わった後のビールも含めて、
野球を楽しんでいる人たちである。
一方プロの選手たちは、
ミクロ単位でシノギを削って野球道を追求し、
人生をかけている人たちである。
そして学問にも、
楽しむ世界と追究する世界とがある。
この著者は、郵便局員を本職とし、
毎日配達をしつつ東大を一般受験して合格する。
大学ではインド哲学を専攻し、
サンスクリット語で原書を読みこなすところまで行く。
いくら好きなことの追究と言えども、
プロレベルを舞台に選ぶひととは、やはりこんなレベルなんね。
ネタバレをしてしまうと、
やはり日常というものに押し戻され、
卒業はするものの、もとの郵便局員で定年退職をしている。
社会で学歴という武器を身につけるという魂胆もなく、
純粋に好きだからという心意気も好き。
その純粋な好奇心や闘争心に、
敬意を表したいのである。
野球をしている場所に
ピン・キリがあったとしても、
このピン・キリとは優劣ではなく、
その人による、楽しい思うこと、
感じ方の違いでしかない。
学問でも、
街中で目につく森羅万象を、
広く求める知的行為もあるし、
ひとつの学問を最高学府の舞台で、
真理まで追求しようとする道もある。
タモリやカズレーザーの博識も、
放送大学でぼそぼそと授業してる先生たちも、
どちらも知識を楽しんでいる人たちである。
それにしても、
趣味をこじらせるとこんなことになってしまうのねという話でもありました。
(敬意とあこがれを込めて)。
映画を見ているときの話で、
主人公がピンチになっても、
「でも、そろそろ終わる時間だから、ダイジョブなんじゃない?」
なんて思ってしまう時がある。
本も、初めの厚さという実感をもって読み始める。
そして途中、ページの進み具合を手で感じながら
「つかみはこんなところからか」
「まだ何か出てくるか」
「そろそろ言いたいことは出つくしたか」という、
もうひとつの無意識下での遊びがある。
私が電子書籍にならない理由である。



