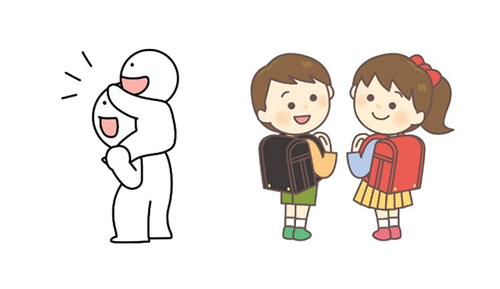1)英語
90過ぎの母がいる。まだ言っている内容に問題はないのだが、いかんせん発声が弱くて聞きとれない。それでも、状況とか表情とかで何とかなっている。
それで気がついたのだが、日常の会話とは、単語10個のうち3個もわかれば何とかなるものなのだということでした。
英語がまるっきりなのだが、今思えば、数少ないあの時あの場面で、耳を澄まして知っている単語を少しでも拾っていけば、その先の道もあったかもしれないとも思ったのでした。
…しかしその前に…、
人間としてのコミュニュケーション能力の問題から、西洋人に「ハーイ~」とこられた瞬間、心のシャッターを下ろし臨戦態勢に入っていたものでした。

昭和の時代、なぜか英語が主要五科目に組み込まれ、ということは、「英語ができる=勉強ができる」という誉め言葉になりました。
「羊と家具」。人生の中で何回使われるのかというこの言葉を、これは単複同形で三単現のSはつきませんと、中学の英語の先生は得意になって教えてくれました。
英語教育とは、英語圏に敬意を表するためにわざとトンチンカンで教えていたのかとか、役人や教師は生活のためにそのオキテを守っていたのかとか、いまだに恨みを込めてぶつぶつ言っています。
そしてそのまま今日まで何でもないのですが、そんな遠い目で嘆いているうちに、携帯の翻訳機能がかなり実用的になっているようです。私のパスポートは切れたまま、ひとり旅は国内で満足しているので関係ありません。

2)国語

やはり勉強に必要なのは、国語力です。
“勉強”というと、いくらかネガティブなイメージが浮かんでしまいますが、「知識を得る」という広い意味を勉強というとすると、
勉強(知識)は食べ物と同じで、生きている間は常に摂取し続けなければならないものです。
国語力は、勉強の基礎体力です。書物を言葉として読めたとしても、全体の空間認識力が必要です。理解速度も重要です。
世の中はその人間の長所を、時間をかけて選考する親切はしてくれません。応答に読解力と速度を持った国語力は、強力な武器となります。

国語力は、大人ですと、やはり自分から本を手に取って読むというところからでしょうか。ちょっと意識することによっていつでも勉強はできます。
子供の国語力は、いまだに研究対象になっているほど、驚異的な上達速度をみせます。物心つく前から、よく話しかけてあげて、話を聞いあげて、本を読んであげて、本を読む機会を与えてあげること、これが能力UPの方法です。