3)紀元1世紀と、2世紀。
(西暦0年から200年まで)

そして西暦が始まって、ここからは100年(1世紀単位)で見てみます。
まずは最初の100年×2、この「2世紀」は弥生時代です。
授業では弥生時代は一瞬で終わるので短いかと思われますが、もう少し正確に言うと紀元前3世紀くらいから始まっているので、合わせて「5~6世紀もの間」が弥生時代です。
100世紀の縄文時代と比べると圧倒的な差があるのですが、それでもけっこう長いです。織田信長から今日ぐらいまで弥生時代です。
弥生時代といえば、「大陸から渡来人が一気に農作物の栽培をひろめた時代」と小学校で習いましたが、今はそれより古い遺跡からも農作物の耕作の跡が見つかって、その説は一気になくなりました。(そう書かないとテスト×つけたくせに)

狩猟が中心の生活と農耕生活の違いは、集団生活で行う作業という点にあります。分担という効率化から始まったのですが、そうなるとこんど、収穫物の分配や略奪などという、今までで思いもつかなかった課題がでてきました。そこでリーダーというものが必要となってきます。
そしてこの辺りから「統治」というイメージがでてきます。クニという概念と王様の出現です。話し合いによるルールの作成までにいたるのはまだ少し先で、神によるお告げという方法で統治は行われます。宗教集団は現代も同じです。

遺跡からの人骨を見ると、思った以上に外傷の跡が多く見られるそうです。この時代もイラストで見ると温和な人たちというイメージばかりで書かれていますが、手加減を知らない幼稚性も持ち合わせているのかもしれません。現実は人間らしい側面を見せてくれます。

西暦57年(1世紀の中頃)中国の書に、中国の王様が、あるひとつのクニに、「倭の奴国王(わのなのこくおう)に金印(ゴールドの印鑑)をあげた」という記述があります。
これだけならばたいした話ではなかったのですが、この金印が1800年後の江戸時代に「裏の畑を耕していたとき」にでてきました。
当然、当時としても「…??」となったのですが、近年になって金の不純物が古代のものと一致していることが証明され、本物ということになっています。現代なら話題作りにユーチューバがやりそうですが、江戸時代に不純物を考慮する知恵や技術はなさそうです。
某元首相の暗殺事件も、手製の銃なんかで暗殺はできないというもっともな意見と、あれだけの多くの人たちが関わっているなかで完全な秘密裏に行うことは不可能という意見とがあり、こちらはまだです。
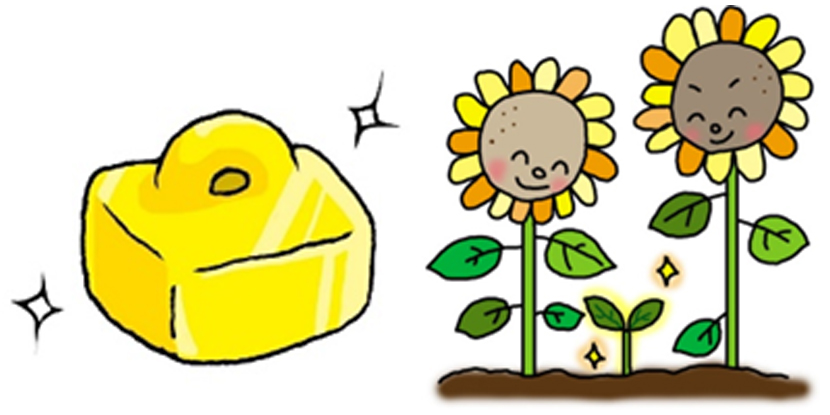
「日本の古代2」に続きます。



