3)ウィルスの薬
ウィルスはあまりに構造が単純なため、
簡単に変性をします。
「細菌の進化」を、
部品が新しいものに交換され、
パソコン全体の性能アップしたするものとすると、
「ウィルスの変化」とは、
もともとがUSBメモリーみたいなものなのであり、
情報書き換えでどんどん進化していってしまう、そんなイメージです。
(「コロナウィルスが次々と変化しています」というニュースをこんな感じに、勝手に解釈していました。)
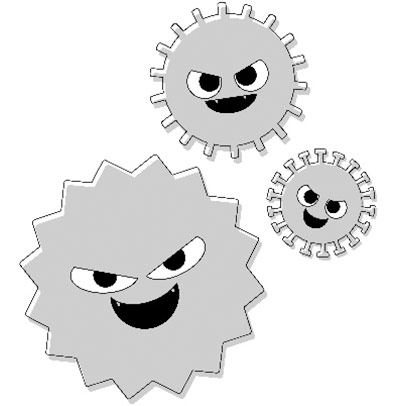
そしてウィルスの薬は、ほぼありません。
なぜならば小さなウィルスを、
特定するのがまず手間であり、
それに見合う薬を開発するのはさらに手間であり、
そして開発できたところですぐ役に立たなくなってしまうからです。
自然淘汰が、自然の摂理なら、
利益の望めない研究をしないのも、人間の摂理です。
インフルのタミフルとかHIVウィルスの増殖を抑える薬、
C型肝炎・ヘルペスあたりの薬がありますが、
確かに商業ベースに乗っていそうなものばかりです。
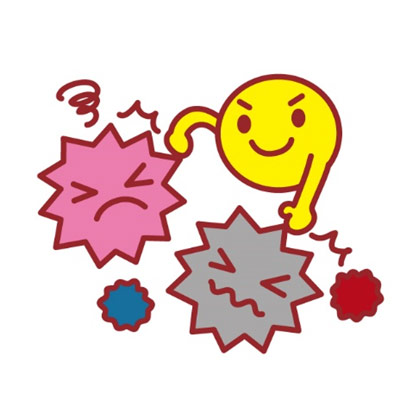
そこでワクチンの開発となります。
ワクチンとは、細菌に対する抗生剤のように
殺菌的役割を期待する薬ではなくて、
ウィルスを攻撃する体内の機能、
免疫力を高める薬です。
よって「ウィルス疾患の治療」の基本は、
生体内で
「ウィルスが弱毒化するまでの時間」
の話になります。
言い換えると、
医療は「それまで耐えうる体力」
というものに力は注がれます。
体力が少し脆弱な、老人・子供・基礎疾患を持っている人は、
特に注意が必要となる理由です。
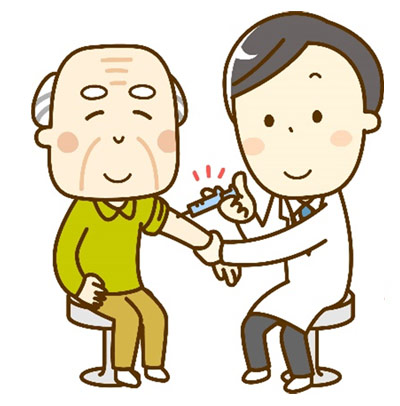
4)につづく



